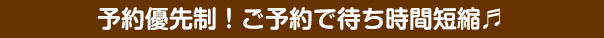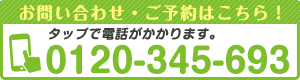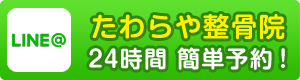捻挫
捻挫について 頚椎捻挫=ムチウチ症

■捻挫について
<捻挫の発生と症状>
関節には動かせる範囲があります。その範囲を超える動きを強制されたときに、関節の組織が損傷するのが捻挫です。「ぎっくり腰になった」、「足首をくじいた」、「突き指をした」などが日常生活でもっとも起きやすい捻挫の例です。交通事故で多いケガの「むち打ち症」も捻挫の一種です。
動かせる範囲を超えて関節を曲げると、関節を包んでいる「関節包」や骨と骨をつないでいる「靭帯」、その周辺の腱などの「軟部組織」が損傷します。それによって、痛み・腫れ・熱などの症状がでます。
関節のケガでも、骨と骨との位置関係がずれてしまったものは脱臼といいます。捻挫は骨と骨の位置関係には異常がない、関節組織の損傷です。
<捻挫の治療―急性期>
捻挫の治療はまず、患部の視診から始まります。異常に腫れあがっているときは骨折や靭帯の断裂が疑われるので、整形外科ではレントゲン撮影で、接骨院では超音波検査器などでたしかめます。つぎに、炎症(腫れと熱)と痛みを軽くする「冷却」とケガをした関節を動かさないための「固定」をおこないます。
アイシング(冷却)―炎症はケガを治そうとして血液やリンパ液が患部に集中することで生じます。つまり人の自然治癒作用にともなう現象です。壊れた細胞組織や内出血した血液を運び去って、新しい組織をつくるためにふだんより大量の血液やリンパ液が必要なのです。しかし、この反応は過剰になりやすいので冷やしてトーンダウンさせる必要があります。
長い時間連続して冷やすのは健康な組織にわるい影響があるので、ときどき中断します。また、あまり長期間アイシングするのは自然治癒を遅らせることになります。
固定―ケガをした組織の修復がある程度すむ前に動かすと、修復を遅らせるだけでなく、さらに傷を広げてしまったり、間違った位置関係で修復してしまうおそれがあります。それを防ぐのが固定です。固定する期間は、ケガの程度に応じて1~3週間です。これを「急性期」といい、ほぼこれくらいの期間で内部のケガの修復は終わっています。
<捻挫のリハビリ―亜急性期>
捻挫した患部の固定が終わると、リハビリの段階に入ります。長い時間固定したことで関節のいろいろな組織が硬直して、機能が弱っています。正しいステップと方法で機能回復させることが必要です。固定が終わってすぐ治療をやめると、また同じ場所を捻挫しやすくなるいわゆる「捻挫ぐせ」がつくことがあります。
テーピング―固定を解いて関節を動かしはじめるときは、関節があまり大きな角度で動かないようにテーピングで動きを制限することがあります。じゅうぶんに柔軟性を取り戻して、筋力も回復する前に大きく動かすと、また捻挫してしまう危険があるからです。
温熱療法―急性期の張れと熱が収まって、固定も終わってからは、冷やすよりもむしろ温めることが回復を早めます。血液循環をうながすことで機能回復が早まるからです。
運動療法―少しずつ関節を動かして筋力を強化し、運動機能を回復します。施術者が手技で関節を動かしてストレッチすることもあります。
機能回復の期間である亜急性期は、ケガをしてから1カ月~3ヵ月です。ほとんどの捻挫はこの期間内に完治します。しかし交通事故のむち打ち症は、首にいろいろな神経が集中しているという特性もあって、症状が長びくケースがあります。3ケ月以後も症状が続く場合は「慢性期」と考えて必要な治療を継続し、場合によっては後遺症の認定を受けることになります。
交通事故施術メニュー
交通事故の治療と
ケース別症状
交通事故の
知っておくべき情報